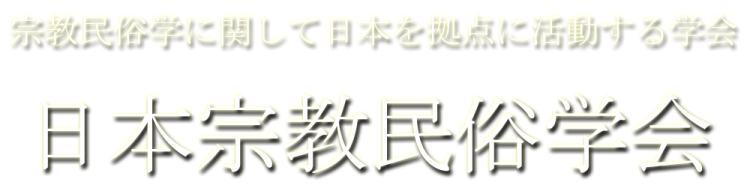日本宗教民俗学叢書
| 著者 | 書名 | 価格 |
| 大森 恵子 | ① 稲荷信仰と宗教民俗 | 14800円 |
| 中澤 成晃 | ② 近江の宮座とオコナイ | 5900円 |
| 藤田 定興 | ③ 近世修験道の地域的展開 | 11000円 |
| 福江 充 | ④ 立山信仰と立山曼荼羅 | 8200円 |
| 奥村 隆彦 | ⑤ 融通念仏信仰とあの世 | 14800円 |
| 伊藤 曙覧 | ⑥ 越中の民俗宗教 | 14800円 |
| 橋本 章彦 | ⑦ 毘沙門天―日本的展開の諸相― | 6400円 |
| 日野西 眞定 | ⑧ 高野山信仰史の研究 | 9900円 |
| 小田 悦代 | ⑨ 呪縛・護法・阿尾奢法―説話にみる僧の験力 | 6000円 |
各書籍の概要については岩田書院ホームページ内の日本宗教民俗学叢書目録(http://www.iwata-shoin.co.jp/iwa_sho/books20.htm)を参考にしてください
学会誌

第35号<特集報告テーマ:文化財と宗教民俗>(2025.03)
基調講演修験道研究の課題と展望 鈴木正崇特集文化財と宗教民俗―2020 年代の今を問うための発題として― 久保田裕道シンポジウムコメント地元軽視と女性蔑視観の終焉を願って 吉川祐子宗教民俗文化財は誰のものか―コメントに代えて― 星 優也研究…
2025.10.17

第34号<特集報告テーマ:「墓」をめぐる視座>(2024.03)
公開講演五来宗教民俗学が究明しようとした本質―総合研究と念仏芸能を中心にして― 大森惠子特集報告英彦山一山における近世墓制の在り方 山本義孝真宗と「墓(石塔墓)をつくらない」民俗 蒲池勢至研究論文宗教集落「嶽」の歴史と伝承―『早池峰山大権現…
2025.06.15

第33号<特集報告テーマ:『神話・伝承と宗教民俗』>(2023.03)
特集報告「タマとカミをめぐる試論」橋本 章彦「生活化する神話世界―関東の二十四輩伝説と風土神の帰服―」堤 邦彦「寺社縁起と『近世王権神話』―栃木県栃木市岩船山高勝寺の事例から―」林 京子研究論文「羽黒山の神子舞と獅子舞―戸川安章の論を手がか…
2023.05.24

第32号<テーマ:地域社会と宗教民俗―正月の神と仏>(2022.03)
公開公演「現代に生きる湯殿山即身仏信仰」岩鼻 通明特集報告「南東北における伊勢参宮と湯殿参詣の意義」原 淳一郎「十五夜の来訪神」永松 敦「正月に去来する鬼と神―播磨の鬼追いを中心に―」小栗栖 健治研究論文「柳田國男「山宮考」における山宮と氏…
2022.03.31

第31号(2021.03)
研究論文「戦国末期の岩船山―新出「下野国岩船地蔵誓願参日記」とその周辺」林 京子「神社の由緒と古墳―丹後網野神社と銚子山古墳―」小山 元孝「光福寺蔵正慶写本にみる六斎念仏の寺院掌握と変容」山中 崇裕研究覚書「山の神」石田 哲彌書評宮家準著『…
2021.03.31

第30号<特集 2019年度大会 日本宗教民俗学会・国際熊野学会合同開催:伝統文化と女性>(2020.03)
特別公演「京都・嶋原太夫の世界」嶋原末廣屋 司太夫特別報告「熊野比丘尼の慣わし―入寺・年籠・姿態を中心に―」山本 殖生「子抱き幽霊図の原風景―産死供養の図像―堤 邦彦「ブータンにおけるシャーマンの治病儀礼をめぐって」本林 靖久研究論文「柳田…
2020.03.31

第29号<2018年度大会特集テーマ 五来重生誕110年記念 五来重の学問を語る>(2019.03)
公開公演「『海洋宗教』研究について」豊島 修特集報告「五来重先生と『高野聖』」根井 浄「五来先生から学んだ勉強法」山田 知子「五来重先生の昔話研究」吉川 祐子「五来重先生の仏教と民俗から仏教民俗学へ」西海 賢二研究論文「念佛院の髪繍六字名号…
2019.03.01

第28号<2017年度大会シンポジウム 花祭再考-五来重の神霊観念を越えて->(2018.03)
特集報告「修験道から花祭りへ―花祭りへの五来重の視点から―」山﨑 一司「花祭における神霊観念の諸相について―「花祭再考」のための試論として―」久保田 裕道「神道花祭再考―岩戸神話と大神楽と花祭―」矢嶋 正幸「花祭研究の現在」井上 隆弘研究論…
2018.03.012023.04.03

第27号<2016年度大会シンポジウム 「穢れ」をめぐる領域間の対話と議論の共有>(2018.01)
特別公演「浄土教の列祖と山岳修験」宮家 準「山・古墳・浄土―日本列島における聖地観の変遷―」佐藤 弘夫「古代・中世における<穢れ>研究の現状と課題―『領域間対話』に向けた準備作業として―」舩田 淳一「穢観念の多様性について―『領域間の対話』…
2018.01.012023.04.03

第26号(2017.03)
「牛頭天王信仰に関する一考察―牛御前社を事例として―」大関 直人「与喜山―山の力と、山と人との距離感の変遷―」吉川 宗明「高野山における遷宮の意義について―『神璽内侍所事』を中心に―」吉田 唯書評日野西眞定著『高野山信仰史の研究』井後 尚久…
2017.03.01

第24・25合併号(2016.03)
「重層的で円環的な神話空間」佐々木高弘「仏画に描かれた日本の“巡礼”」石川 知彦「開帳される弘法の遺品―御衣を中心に―」鬼頭 尚義「頭人差定文書の儀礼と管理―近江大篠原天王社の頭役祭祀を事例に―」渡部 圭一「近世末期、御室配下の六十六部集団…
2016.03.012023.04.03

第23号(2014.03)
「鎮魂の解釈をめぐって―タマフリとタマシズメと―」久保田 裕道「獅子舞と鎮魂」大森 恵子「近現代における真宗と地域社会―真宗道場と道場主の変遷を中心に―」本林 靖久「湯涌ぼんぼり祭りに関する巡礼者の言説を巡って」由谷 裕哉書評西海賢二編『山…
2014.03.012023.04.03

第21・22合併号<特集:新しい宗教民俗へ―他界の形成をめぐって―>(2013.01)
特別講演「日本宗教民俗学会の歩みについて」鈴木 昭英「霊魂観の成立」広瀬 和雄「江戸の『あの世』語り―創造される他界―」堤 邦彦「民俗知の生成と篤胤の『幽冥』論」斎藤 英喜「霊場恐山にみる他界の構造」鈴木 岩弓全体討論「御獄講登拝を支えた女…
2013.01.012023.04.03

第20号<特集:裸祭の今昔>(2010.9)
「上賀茂神社の特殊神事について」建内 光儀「浦佐毘沙門堂裸押合いの昔と今―祭式儀礼を中心として―」鈴木 昭英「西大寺会陽にみる寺方戦略の変遷」根木 修「裸祭り考―なぜ奈良県に裸祭りはないのか―」吉川 雅章「前田利常を顕彰する祭礼の形成と変遷…
2010.09.012023.04.03

第19号(2009.11)
「死者と仏教―柳田国男から五来重へ―」碧海 寿広「中世における日中貿易守護と琵琶法師守護に関する弁財天信仰―特に、大覚寺弁財天堂に寄せられた信仰と西園寺家の川の神信仰を中心に―」大森 惠子「伊勢大神楽にみる「霊性」「聖性」の付与―信仰が地域…
2009.11.012023.04.03

第18号<特集:仏教と民俗>(2008.12)
「仏教と民俗の交渉―修験道史研究をふまえて―」豊島 修「日本的念仏の三円構造」坂本 要「熊野信仰と湯立神楽」鈴木 正崇「五来重と仏教民俗学の構想」林 淳「オコナイへの視線―地域の宗教史と民俗学の挟間で―」和田 光生新刊紹介『五来重著作集 …
2008.12.012023.04.03

第17号<特集:新しい宗教民俗論の構築-「真宗と民俗」の再検討->(2007.10)
「真宗と民俗―思想史の視点から―」大桑 斉「近江の『廻り道場』―近世後期における「惣」道場の一形態―」松金 直美「習合宗教系『隠れ念仏』講と真宗講の年中行事比較に見る民俗―宮崎県都城市水流町を中心として―」森田 清美「真宗門徒の日々―民俗語…
2007.10.012023.04.03

第16号<特集:地獄・極楽図と宗教民俗>(2006.12)
「地獄絵の東漸―『熊野観心十界図』への道―」林 雅彦「『熊野観心十界図』と<心>字―『観心十界図』『二河白道図』との関わりから―」石黒久美子「出光美術館本 六道十王図に見る伝統と地域性」鷹巣 純「血の池如意輪観音 再考―六角堂・花山院・西国…
2006.12.012023.04.03

第14・15合併号<特集:陰陽道と宗教民俗・特集:聖地と霊木>(2006.03)
特集 陰陽道と宗教民俗「民俗社会のなかの『陰陽師』の存在形態―高知県物部村の『いざなぎ流太夫』の場合―」小松 和彦「甲斐国における中世末期の民間陰陽師の足跡」山本 義孝「『いざなぎ流』研究史の整理と展望」斎藤 英喜「『民間陰陽道』概念の再検…
2006.03.012023.04.03

第13号<特集:天神信仰と天神祭>(2003.12)
「雷の通る道」田中 久夫「太宰府天満宮の古式祭と古式神饌―菅公御神忌一千百年大祭における古式祭典の復元にあたって―」森 弘子「天神祭と講社」澤井 浩一「天神として祀られた藩主―加賀・能登・越中の天神信仰―」西山 郷史「信仰伝播に関する一試…
2003.12.012023.04.03

第12号<特集:異界のカミ・ホトケ>(2002.07)
「稲荷信仰の原点と変貌」村山 修一「病気治療における『解縛』と『辟除』―異常な状態を終結させる呪術に関する一考察―」小田 悦代「近世中期における地方社会の怪異観―『西播怪談実記』を通して―」埴岡 真弓「京都府下に於ける初誕生儀礼」近藤 直也…
2002.07.012023.04.03

第11号(2001.09)
「来訪神祭祀の世界観―宮古島・島尻のパーントゥの事例から―」本林 靖久「山岳霊場のハナ―大峰山のシャクナゲを中心に―」藤井 弘章「桓武から仁明朝における陰陽寮の活動について」村上 知美「かつらぎ町宮本丹生・狩場神社の縁起について」日野西 眞…
2001.09.012023.04.03

第10号<特集:兵庫県三田の民俗>(2000.09)
「三田市域の民俗芸能」山路 興造「三田市の田楽躍―特に芸態と宗教性を中心にして」大森 恵子「年中行事の内と外」西尾 嘉美「お頭神事―株座とその歴史的背景」埴岡 真弓「オコナイの根幹をなすもの―オトウ行事にみる花と牛玉杖―」中島 誠一「両…
2000.09.012023.04.03

第9号<特集:縁起と民俗>(1999.06)
「空海の伝記について」上山 春平「熊野の八咫烏伝承の成立と展開」山本 殖生「半田稲荷社の略縁起と願人坊主」鈴木 明子「高野山の縁起」日野西 眞定「新潟県の石仏の歴史 その1―大和地方からみた中世の歴史―」石田 哲弥「伊勢大神楽の展開―檀那場…
1999.06.012023.04.03

第8号<特集:石と宗教民俗>(1998.06)
「江戸期における融通念仏信仰と作仏聖―信州の石碑石仏を中心として―」宮島 潤子「立山信仰にみる石仏寄進の一例―江戸の信徒による姥堂境内六地蔵尊石像の寄進―」 福江 充「岡山の中世石塔の特色と民俗学的諸問題」尾崎 聡「聖地内巡礼―ミニチュア巡…
1998.06.012023.04.03

第7号<特集:稲荷信仰>(1997.6)
「高野山の蓮花会(下)」日野西 眞定「稲荷信仰の懸仏」山下 立「稲荷信仰と修験山伏―特に狐憑きをめぐって―」菊池 武「狐変化型芸能にみられる宗教者の教化活動―能楽・歌舞伎・人形浄瑠璃のなかの陰陽師を中心にして―」大森 惠子「稲荷大会参加雑感…
1997.06.012023.04.03

第6号(1996.06)
「王の袖は二尺五寸の御利口」平山 敏治郎「臨終の善知識」吉田 清「湖北の真宗道場―方便法身尊像の機能を手がかりに―」脊古 真哉「近世の関東における六十六部について―安房国の廻国納経帳から―」菅根 幸裕「木食正禅養阿の信仰と救済―『木食正禅養…
1996.06.012023.04.03

第5号(1995.06)
「高野山の蓮花会(上)」日野西 眞定「安倍晴明伝説―京の晴明伝説を中心に―」高原 豊明「能楽「小鍛冶」の演出と稲荷霊験談」大森 惠子「中世八幡信仰の窟―豊後国口戸窟の構造とその信仰―」 山本 義孝「擬死再生と逆修」奥村 隆彦「日本宗教民俗学…
1995.06.012023.04.03

第4号(1994.09)五来重先生追悼号
「仏教民俗学に新機軸―五来重氏を悼む―」桜井 徳太郎「熊野新宮の修験組織と活動―近世本願の動向を中心に―」山本 殖生「盆行事と社会組織―鳥羽市石鏡町の盆行事を中心として―」木村 登次「もと高野山の学侶龍淵の在地宗教活動―芦峅寺一山とのかかわ…
1994.09.012023.04.03

第3号(1993.06)
「日記念仏信仰」中上 敬一「廻国行者と天蓋六部―『日本九峰修行日記』の提起する二、三の問題について―」小嶋 博巳「中世宮座論」小栗栖 健治「薩摩・大隅地方の柴の宗教性」永松 敦書評池上廣正先生著作刊行会編『宗教民俗学の研究』本林 靖久
1993.06.01

第2号(1992.09)
「湖北における修正会とオコナイの源流」中澤 成晃「明治以降の土御門系陰陽師」木場 明志「『神峰山寺秘密縁起』の奥書を検証する」橋本 章彦「高海上人と『那珂湊補陀洛渡海記』―解題と翻刻―」 根井 浄「日本宗教民俗学研究上の諸問題を考える(2)…
1992.09.012023.04.03

創刊号(1991.09)
「日本宗教民俗学研究会会誌創刊に寄せて」五来 重「瞽女の宗教性」鈴木 昭英「土と稲荷信仰」大森 惠子「海と黄帝信仰―その実態と伝播―」菊池 武「御嶽講と近世後期の民衆意識」 平野 寿則「日本宗教民俗学研究上の諸課題を考える(1)聖(ヒジリ)…
1991.09.012023.04.03